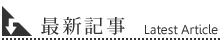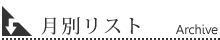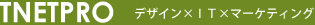in SEASON 11月号は「祝子農園」と「宮崎ひでじビール株式会社」をご紹介!
☆in season 11月号のお知らせです☆
今月の生産者特集は、延岡市にて祝子農園を営む松田宗史さんをご紹介します。
農薬や化学肥料に頼らず、植物本来の力を最大限に発揮させることでおいしい米づくりを心掛けておられます。
「今月の生産者」にて、詳しく紹介しています。
美和の宮崎出逢い旅は、同じく延岡市で宮崎ひでじビール株式会社を営む永野時彦さんをご紹介します。
全国でも珍しい100%自家培養のビール酵母を使用しているひでじビール。現在まで至るには苦難の連続がありました。
「出逢い旅」にて、詳しく紹介しています。
また、本日より、in SEASONフリーペーパー11月号の配布も始まっております。
詳しい配布場所についてはこちら。
そして、今月も読者プレゼント企画がございます。フリーペーパーに載っているキーワードをチェックして、是非ご参加ください♪

更新日時:2013.11.05(火) 12:11:05